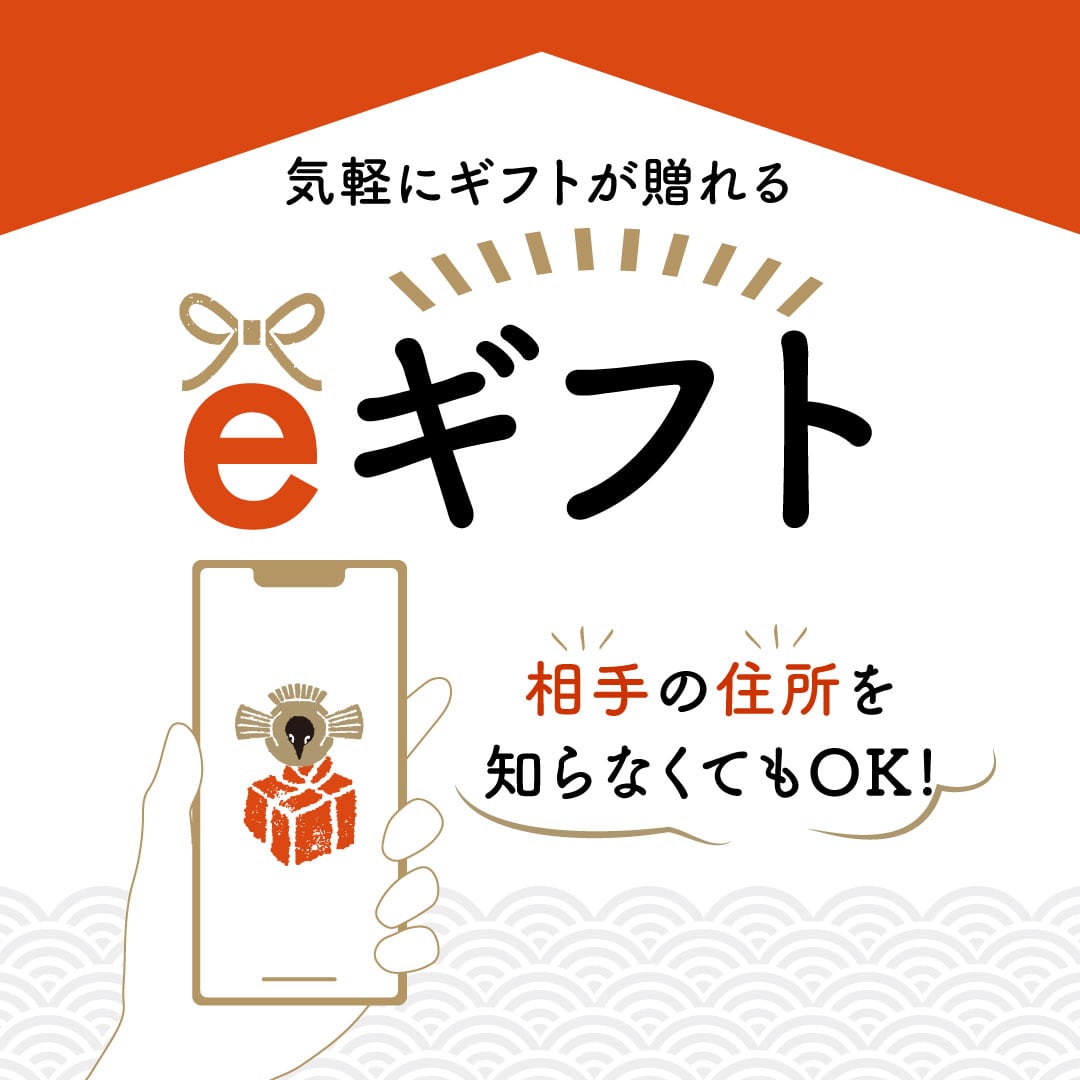普段なにげなく使っている醤油ですが、その醤油にもさまざまな種類があります。
その醤油の種類によって、どんな料理に合うかも違ってくるのです。
今回は、醤油の種類の違いと使い分けについてご紹介します。
醤油の基本工程
醤油の「原材料」は、大豆・小麦・麹菌・塩・水。
大豆は蒸し、小麦は炒って、種麹を加えて麹菌を繁殖させます。
その麹菌が大豆のタンパク質をアミノ酸に、小麦のでんぷんをぶどう糖に分解します。
次に塩水「汲み水」をその麹に入れて「諸味(もろみ)」をつくります。
この「もろみ」の状態で半年から数年ほど発酵熟成。
この間に乳酸菌による乳酸発酵で糖の一部が有機酸に変わり、酸性になると酵母菌が増加。
酵母菌がぶどう糖からアルコールを生み出し、有機酸と反応します。また小麦の皮の部分から熟成香を出し、風味に深みが出ます。
そうして熟成したもろみを「圧搾」して生揚醤油を搾り出し、その生揚醤油に「火入れ」をして微生物を殺菌、色を濃くし、香りを出します。
最後にろ過をして充填し、完成となります。
この「原材料」の内容、「汲み水」の量、「諸味」の熟成期間、「火入れ」の具合によって、醤油の種類が変わってきます。
その醤油の種類によって、どんな料理に合うかも違ってくるのです。
今回は、醤油の種類の違いと使い分けについてご紹介します。
醤油の基本工程
醤油の「原材料」は、大豆・小麦・麹菌・塩・水。
大豆は蒸し、小麦は炒って、種麹を加えて麹菌を繁殖させます。
その麹菌が大豆のタンパク質をアミノ酸に、小麦のでんぷんをぶどう糖に分解します。
次に塩水「汲み水」をその麹に入れて「諸味(もろみ)」をつくります。
この「もろみ」の状態で半年から数年ほど発酵熟成。
この間に乳酸菌による乳酸発酵で糖の一部が有機酸に変わり、酸性になると酵母菌が増加。
酵母菌がぶどう糖からアルコールを生み出し、有機酸と反応します。また小麦の皮の部分から熟成香を出し、風味に深みが出ます。
そうして熟成したもろみを「圧搾」して生揚醤油を搾り出し、その生揚醤油に「火入れ」をして微生物を殺菌、色を濃くし、香りを出します。
最後にろ過をして充填し、完成となります。
この「原材料」の内容、「汲み水」の量、「諸味」の熟成期間、「火入れ」の具合によって、醤油の種類が変わってきます。